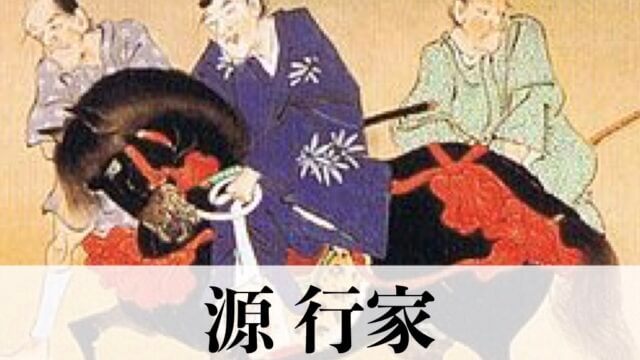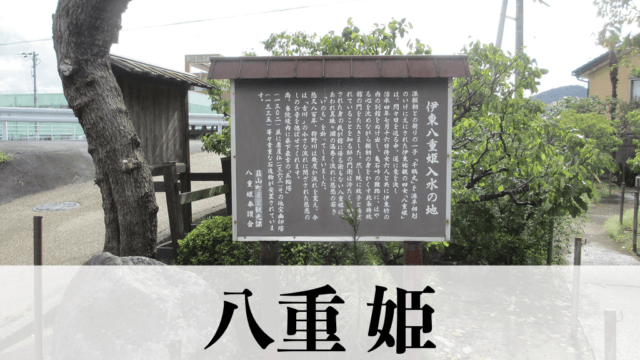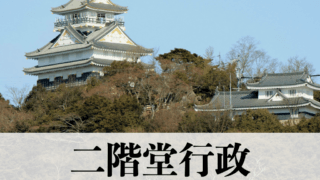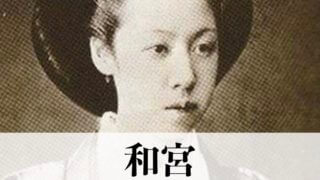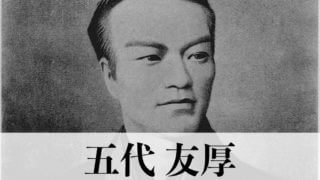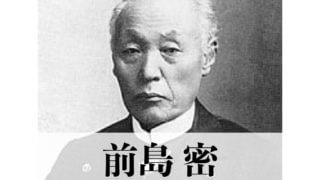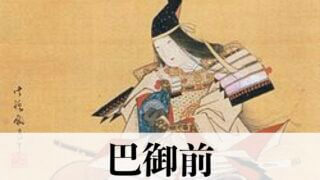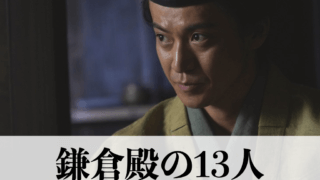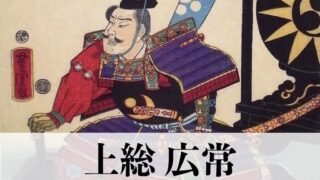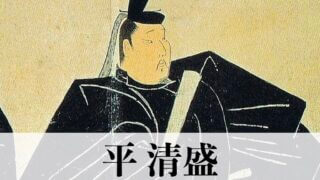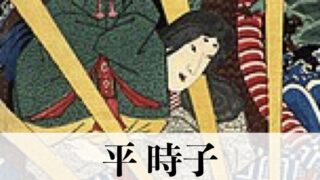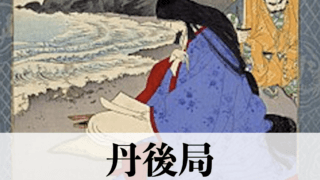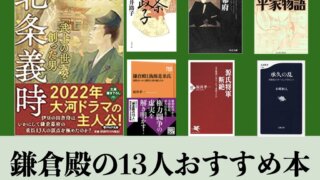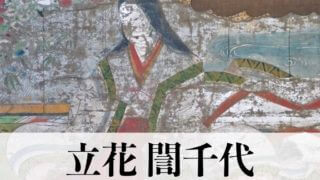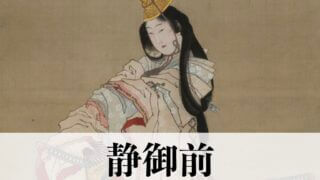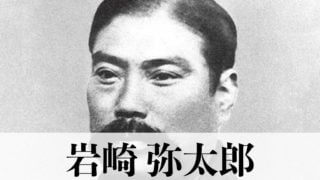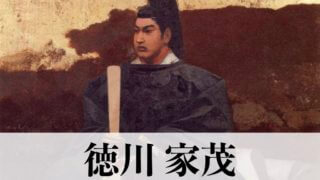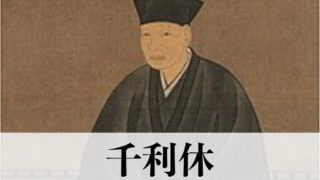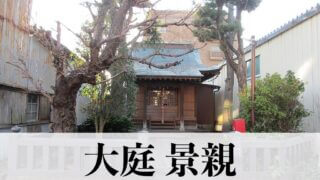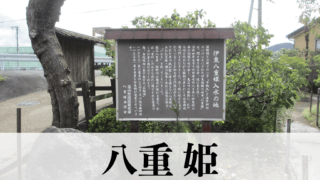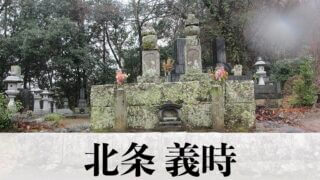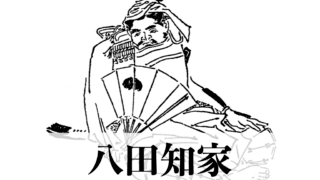どもども、武将好き歴史ファンのジョーです。
今回は、歴史上の人物でも一三人の合議制の1人になったのが「中原親能」ですね。
一三人の合議制は、「鎌倉殿の13人」という大河ドラマでも描かれていますね。
「中原親能」の簡単な略歴は以下ですね。
中原親能のプロフィール
- 1143年:誕生
- 1192年:鎌倉幕府発足
- 1209年:死去
この記事でわかる事としては、「中原親能」の縁の物事、いわゆる「中原親能」の周辺情報についてまとめています。
今回は、「中原親能とは何者だったのか?鎌倉時代の鎮西奉行としての活躍や家紋を紹介:十三人の合議制の一人」と題してご紹介して参ります
ぜひ、勉強に役立てて下さいね。
それではさっそく見ていきましょう!
関連するおすすめ記事
中原親能とは何者か?
こちらでは、「中原親能」とはどのような人物だったのかについてご紹介して参ります。
中原親能は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての下級貴族でしたね。
鎌倉幕府の文官御家人となっていきました。
その後、十三人の合議制の一人に選ばれています。
中原氏庶流貞親流の広季の実子または養子として記録されています。
鎌倉幕府初代将軍源頼朝の側近であり、頼朝の代官として東西に奔走し、朝廷と幕府の折衝に努め、幕府の対公家交渉で大きな功績を果たしたという名将でしたね。
関連する記事
源頼朝とは何者か?お墓や死因、妻たちを解説:平氏を倒した鎌倉幕府の初代征夷大将軍のおすすめ本や大河を紹介
中原親能が務めた鎮西奉行とは?
こちらでは、中原親能が務めた鎮西奉行についてご紹介してまります。
鎮西奉行は、鎌倉幕府で九州の御家人の指揮統制を行った職のことを示しています。
1185年に源頼朝が天野遠景にこの職を任命しています。
そこから、九州の御家人の指揮統制にあたらせたのが始まりですね。
平家の残党及び源義経一党らの追捕がもともとの任務であ李ました。
しかし、その後全九州の御家人の統轄にあたるようになり、大宰府の機能も継承しています。
天野遠景の後について、中原親能が後をついだのがこの職です。
その後、鎮西奉行に代わり新たに鎮西探題が設置されています。
関連する記事
源義経とは何者か?死因やチンギスハンと同一人物と呼ばれた男のおすすめ本や大河ドラマを徹底解説
中原親能の家紋
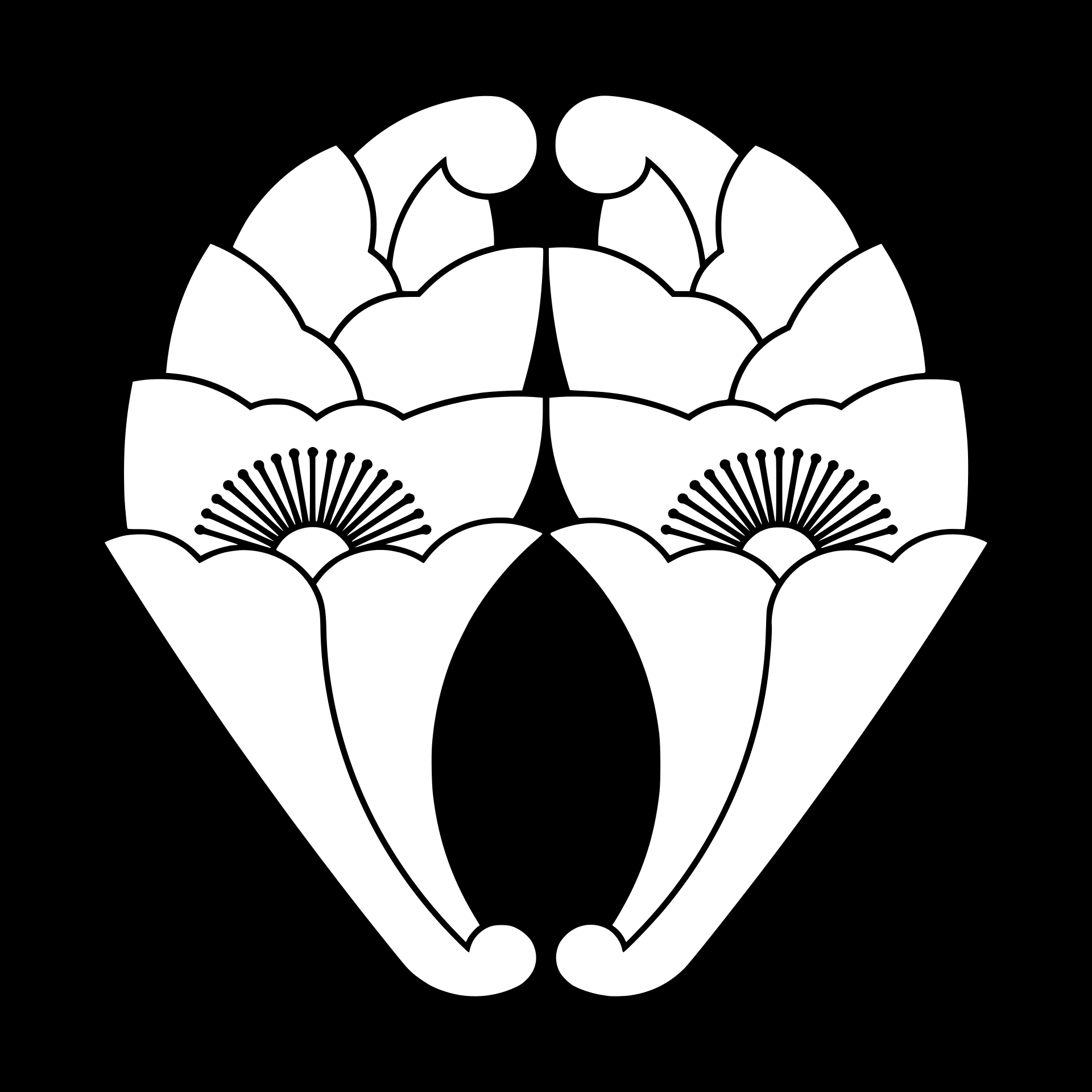 引用;https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E6%B0%8F#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Daki_hana_Gyouyou.svg
引用;https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E6%B0%8F#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Daki_hana_Gyouyou.svg中原親能の家紋は、抱き花杏葉と言いますね。
中原親能と大江広元の関係
こちらでは、中原親能と大江広元の関係についてご紹介しています。
この2人は、十三人の合議制のうちの13人の中に含まれています。
ちなみに、十三人の合議制は大河ドラマ「鎌倉殿の13人」として描かれますね。
関連する記事
大江広元とは何者だったのか?お墓や家紋、源義経や毛利元就の祖先の関係性を紹介!大河ドラマ鎌倉殿の13人に登場する功巨
中原親能のまとめ
如何でしたでしょうか?
以上、「中原親能」についてご紹介してきました。
今回は、「中原親能とは何者だったのか?鎌倉時代の鎮西奉行としての活躍や家紋を紹介:十三人の合議制の一人」と題してご紹介致しました。
ぜひチェックしてみて下さい。
それでは、今回はこの辺で。
関連するおすすめ記事
源頼朝とは何者か?お墓や死因、妻たちを解説:平氏を倒した鎌倉幕府の初代征夷大将軍のおすすめ本や大河を紹介
源義経とは何者か?死因やチンギスハンと同一人物と呼ばれた男のおすすめ本や大河ドラマを徹底解説
大江広元とは何者だったのか?お墓や家紋、源義経や毛利元就の祖先の関係性を紹介!大河ドラマ鎌倉殿の13人に登場する功巨